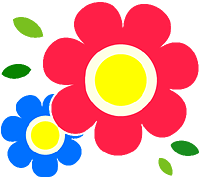1・・・村八分・・・
江戸期以来、一昔前までの農業では余り機械化も進んでいなかった為、米作りの全ての
局面において共同作業が必須であり、ひいては村落における色々な慣例行事においても
助け合いが求められました。その秩序を保たないと村全体の崩壊につながるだけに違反
した人間には村民全部が申し合わせて制裁を加えました。それが村八分です。つまり冠・
婚・葬・建築・火事・病気・水害・旅行・出産・年忌の10のうち葬と火事以外の付き合いを
しないという事です。元来こういう意味だったのですが現代のように近代化が進みそれほど
共同しなくても一戸でできるようになると村八分という言葉は「除けものにする」という意味
で使われるようになりました。
2・・・隠れた村八分・・・
私はいま東日本大震災のある被災者の方々のそばで活動していますが、他の被災者
の状況とは少し様子が違います。よく貧富の格差という言葉が聞かれますがその向こう
には貧困者間の格差、障害者間の格差、被災者間の格差があること長くダウン症児に
そして神戸の大震災の被災者に関わってきた体験から実感しています。震災後の被災者
への援助は多少の政治の遅れはあったにしろそれなりに進んでいるし末端の行政の人々
も被災者自身もボランティアも本当に頑張っていると思います。ただ人の心には善悪では
なく温度差というものがあります。端的にいえばすぐに助けたいと思う人と後回しになる人
がいるということです。この後回しにされるのがある意味、もと住んでいたとこで嫌われて
いた人達、ある意味村八分だった人たちです。昔事件起こした人、乱暴な人、夜の仕事の
人から挨拶しない人まで含まれます。何事もない時は別に大きな問題にはならないのです
が震災のような大事になると大きな差が出てきます。
3・・・ただ淡々と・・・
良い悪いではなく誰しも感情はあるので援助に差をつけるのはごく自然なこと、一方
嫌われている人もその日頃の態度を云々しても余り意味のないこと、援助されて当然と
いう人もいれば有難うひとつない人一杯います。だから普通のボランティアさんは敬遠し
必然的に援助は後回しに或いはゼロになっていきます。結果仮設の中でも孤立していく
ことになっていきます。人間が人間である限りこれからもこうした差は続くと思います。
ではどうするのがいいのかと聞かれればひとこと「ただ淡々と寄り添うのみ」と。大切なの
は安易に善悪の判断を下さないことかと。他人に対しても勿論ですが自分に対しても
同じことかと。いいことしてると思った途端、ボランティアは終わります。人から嫌われてる
人はとても敏感ですから善人の嘘はすぐにわかります。こちらはただ淡々と黙々と。世間
から嫌われてる人にパンが届くのはいつも最後になります。こんな時、綺麗ごとをいっても
始まりません。ただせめて届かないのだけは食い止めたいと思っています。
2013年3月号 ![]()